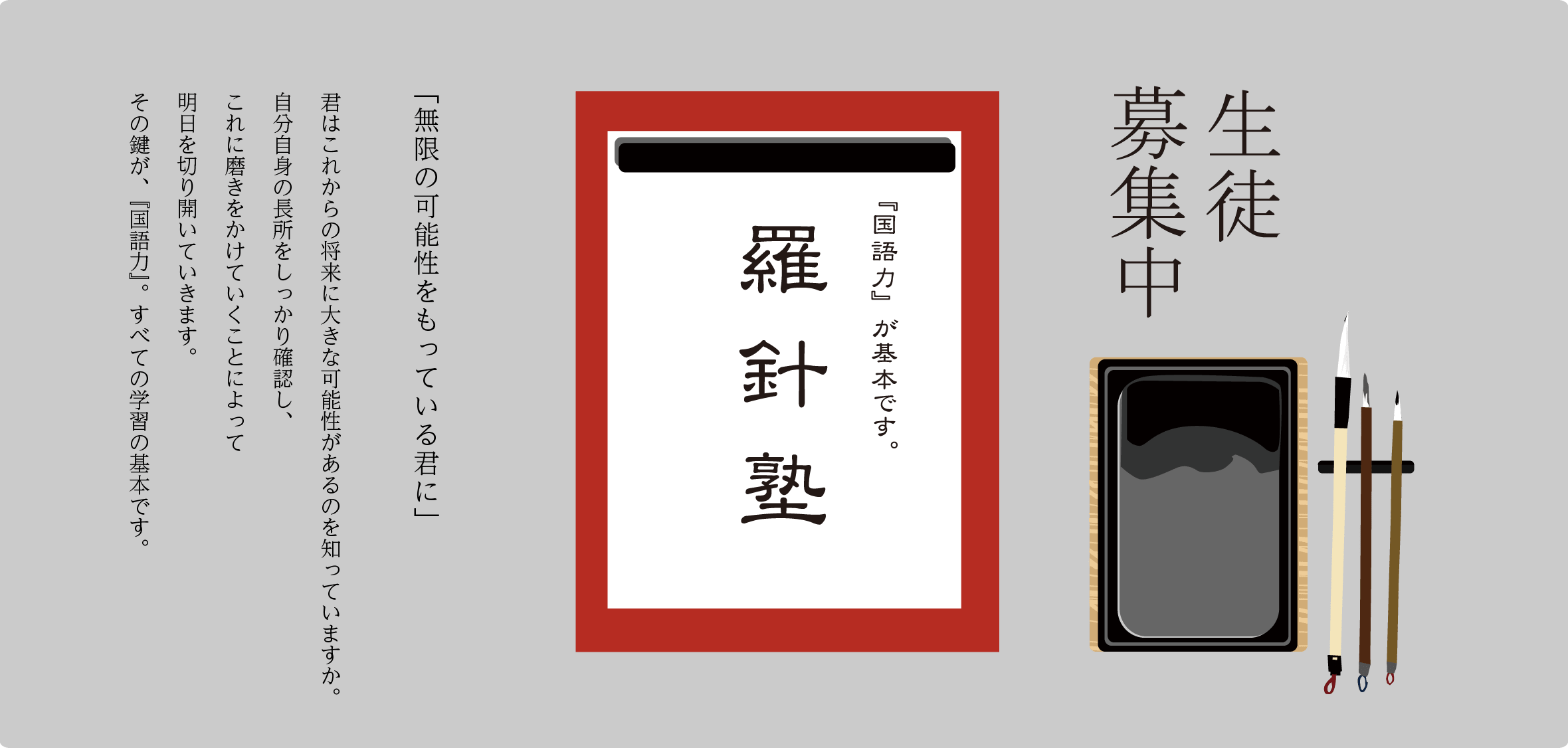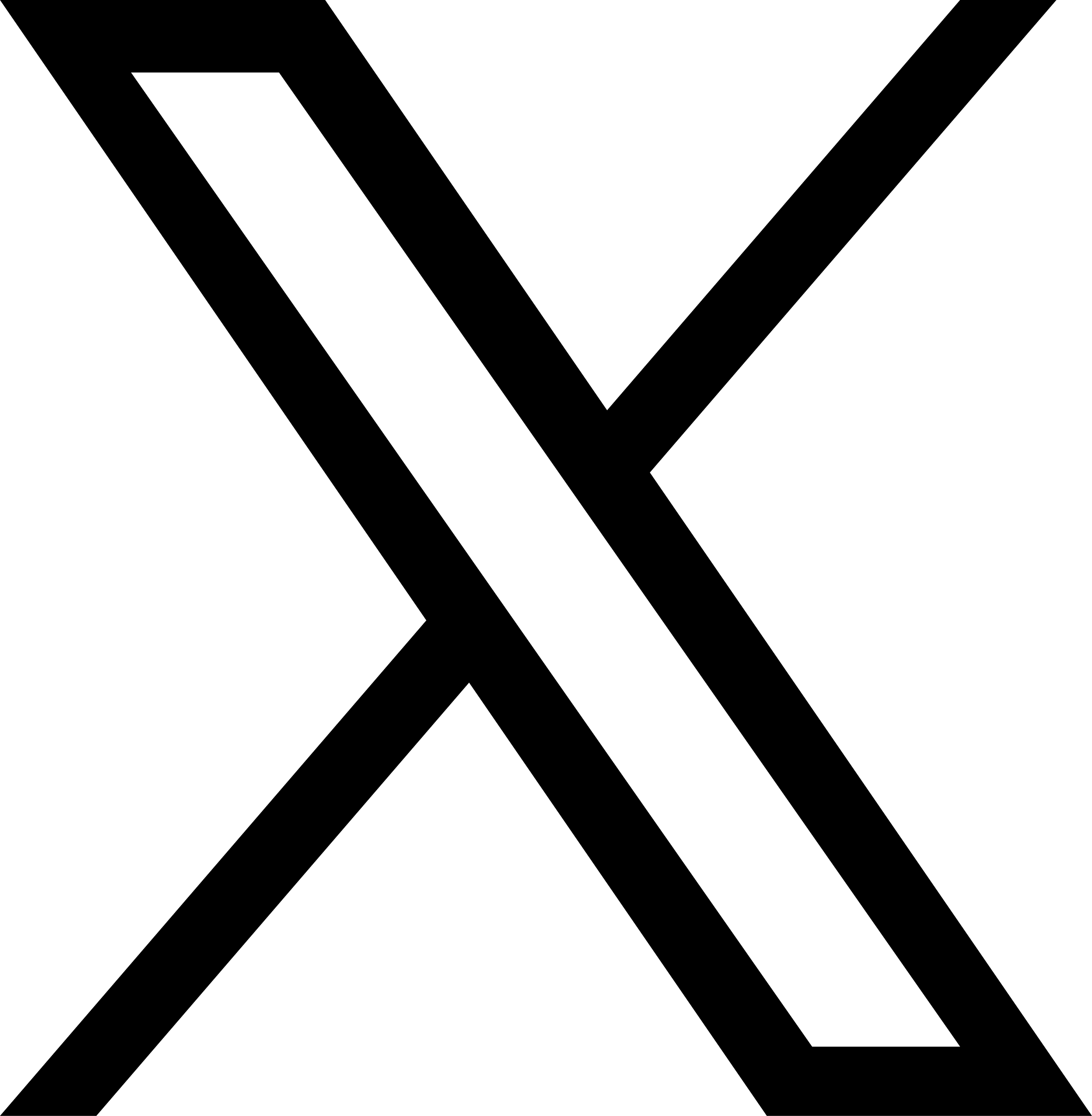長崎市五島町にある羅針塾 学習塾・幼児教室 https://rashinjyuku.com/wp は、「国立大付属校」の入学抽選化を文科省の有識者会議が提言したことを興味深く注視しています。
この提言は、平成29年(2017)8月29日に文部科学省の有識者会議が、国立大学の付属校が「エリート化」し、本来の役割を十分に果たせていないとして、学力テストではなく抽選で選ぶことなどを求める報告書をまとめたものです。学習能力や家庭環境などが違う多様な子どもを受け入れ、付属校での研究成果を教育政策に活かし易くすることが目的で、2021年度末までに結論を出すよう各大学に求めています。
・・・国立大学付属校の本来の役割は、教員養成のため教育実習を実施し、実験的な学校教育を行うなど教育研究をサポートすることです。しかし、有識者会議では、一部の学校がエリート校化してしまい、教育課題への取り組みが不十分だというのです。これは、関東圏や関西圏、教育熱の高い地域の国立大付属のエリート校にその傾向が強いことを指します。
現在国立大付属校は、全国で256校あり(幼稚園49、小学校70校、中学校71校、高校15校など)約9万人が通っています。そのうちエリート校と称される学校では、学力の高い児童生徒が集まるため、多種多様な子どもたちにどんな教育が効果的かというような研究ができないという批判がこれまでもありました。
特に最近では、発達障害や外国人の子どもへの教育支援のニーズが高まっていて、国立大付属校には「本来の役割を果たしてほしい」との声もあるのは事実です。
これに対して、
● 選考方法に抽選を導入すると、国立エリート校の学力低下の恐れがあること
● 経済格差が学力の格差になる恐れがあること といった反対意見もあります。
更に、
文部科学省の有識者会議に対し、RIETI(独立行政法人経済産業研究所、英語名称:The Research Institute of Economy, Trade and Industry)https://www.rieti.go.jp/jp/に、真っ向反対意見を論じている記事を見つけました。
山口一男客員研究員・シカゴ大学ラルフ・ルイス記念特別社会学教授の興味深く参考になるご意見です。
「失敗の歴史から学ばない教育政策―国立大学付属校の抽選入学制度について」
https://www.rieti.go.jp/jp/columns/a01_0483.html(全文を引用致します)
文部科学省の有識者会議が、国立大学付属校の入学についてテストでなく、抽選で選ぶなど入学における「学力偏重」を是正せよとの報告書をまとめた。国立大学付属校が「エリート化」し「本来の役割」を果たせないことが問題だという。単直に言って愚策である。後述する「学校群制度」や「ゆとり教育制度」の二の舞になることは火を見るより明らかだ。つまり、この政策により教育機会の不平等が増す。その理由を、中等教育(中学・高校)を例にとって説明しよう。説明には幾つかの、実際に成り立つ、以下の仮定をする。
教育機会の不平等を増加させる政策のメカニズム
仮定1:比較的安価で、家族の収入によらない基準で手に入れることが可能な質の高い公教育が存在する。
仮定2:質の高い教育の前提として、質の良い「サービス利用者(学習能力の高い生徒)」の存在が一因として存在する。
この仮定は平均的に学習能力の高い生徒だからこそ、高度な内容の教育が提供でき、また成功する傾向を意味する。教育の「コンテクスト効果」と呼び、これは実証されている。
仮定3:しかし、為政者はこの「公的サービス(公教育)」の利用者や、その内容に「学力偏重」があることを嫌い、政策介入を加えて、その「偏り」を除こうとする。
仮定4:学力を重視する大多数の旧制度の潜在的利用希望者は、政策介入後の新制度を嫌い、代替えの選択をしたり、他の制度の利用で補完したりしようとする。しかし、質的に同等な教育は、旧制度と同等に低い価格では得られない。
この仮定はそれまでの優れた公教育の同等な代替は、優れた私立校や、質の良い学習塾でしか補うことができないため、経費が高くなることを意味する。これらを仮定すると以下の結果が得られる。
結果1:政策介入後の利用者(入学生徒)の平均的学習能力が下がり、もはやコンテクスト効果は期待できないので、新制度は以前のような質の高い教育は提供できなくなる。
結果2:旧制度の潜在的利用者のうち、経済的に裕福な家庭の子女は、より高い対価を払って、同等な質の教育を受けられるが、裕福でない家庭の子女は、同等な質の教育が得られず、貧富による教育の機会の不平等が生まれる。
結果3:比較的裕福な家庭が、教育により高い価格を支払うようになるので、教育費が平均的に高くなる。
同様の失敗を招いた過去の例
具体例として、1967〜1981年に東京都が施行した学校群制度がある。制度導入以前は、日比谷、戸山、西、新宿などの都立高校が東大進学者数のトップを占めていたが、学校群導入後のこれらの都立高校の東大進学者数は一桁代に陥落し、一方開成、麻布、灘などの有名私立高校の東大進学率が躍進した。比較的裕福で学力の高い子どもを持つ家庭が都立高校を見放し、有名私立高校に鞍替えたからである。これは質の高い教育を得ることが家庭の経済状態により依存することを意味し、その結果東大進学者の親の所得が増大し、以前に比べ貧しい家庭の出で東大に進学する学生の割合が減る結果となった。「エリート都立高校」を無くそうとする政策は皮肉にも家庭環境によるエリート教育の機会の不平等を増大させたのである。後に都は学校群政策の失敗を認め廃止したが、もはや覆水盆に返らずであった。
1980〜2000年代の公立の初等・中等教育における「ゆとり教育」も同様な結果をもたらした。「知識の詰め込み」に反対し、「生きる力をつける」などと喧伝された教育であるが、平均的に求める学力のレベルを下げたため、学力低下を招いた。当然子どもの学力向上に関心のある親の多くが「ゆとり教育」に不安を持ち、学習塾の利用が増し私立中学への進学率も増大した。またその結果教育費用は高騰し、貧富の差による質の高い教育機会の不平等を生み出したのである。苅谷剛彦東大教授(当時)によると、「ゆとり教育」導入後の学習塾を含む、学校内外の学習時間は中産階級の子女では以前と変わらなかったが、労働者階級の子女では低下し、社会階層による学習への「意欲格差」をも生み出した。
進化ゲーム理論によると、人々が努力をするか否かは社会でその努力が報われる度合いに依存する。進学塾や有名私立の中高一貫校に通わないと、比較的安価な国立・公立大学に進学できないのでは、労働者階級の子女にとって努力が報われる可能性は大幅に減ってしまう。こうして、「生きる力」をつけるはずのゆとり教育は、貧富による教育機会の格差を増大させ、労働者階級の子女に対し努力が報われる機会を減らし、学習意欲という生きる力を奪う結果となった。
今回提案の国立大学付属校の抽選入学制度は、同様な結果をもたらすだろう。国立大学付属校は、優れた進学校ではなくなり、中産階級の子女は優れた私立校に行き、そうでない子女は相対的に教育の質の劣る公立校に進むことになるだろう。一例だが筑波大付属や、筑波大付属駒場などは、戦後の人材輩出度において卓越している。地方国立大付属校にも同様なことがその地方において言えるものは少なくない。これらの付属校の卒業生の一部は家庭環境でもエリートの出であろうが、そうでない者の方が当然多い。これらの付属校の質を変えて、非エリートの家庭から同じように優れた人材を社会に輩出できる保証は全くない。
人材輩出の機能を失わずに本来の目的も叶えよ
また国立大学付属校の「本来の目的」は、多様な背景を持つ生徒への実験的教育による教育方法の研究にあるというのが今回の施策提案の理由だが、優れた教育方法は学習能力と独立ではない。たとえば新しいアイデアを生み出すのに必要とされる「批判的思考」の育成は比較的能力の高い生徒にのみ有効であることが知られている。抽選にすれば、平均的能力を持つ生徒への教育法の研究法には資するだろうが、学習能力の高い生徒に対する優れた教育方法の研究には資さない。ゆえに「本来の目的」でも現行制度の選抜方法を維持しなければできないこともある。また優れた人材の輩出のためには、多様な潜在的才能を伸ばす「英才教育」の研究は極めて重要である。国立大学付属校が家庭環境の上で「エリート化」しているのであれば、入学試験だけではなく、公立中学の成績評価の入学への比重を増やすなどして、家庭環境でハンディキャップを負う優秀な生徒がより入学しやすい仕組みで補完すればよい。
政策は意図せざる結果を生む可能性を常に考慮しなければならない。今回の報告書の提案は、日本が未だ学校群制度やゆとり教育制度の、意図せざる失敗の原因について、何も学んでこなかったことを示唆する。国費での「エリート教育」に反対するというのは偽善である。それならば、いっそのこと東大・京大などのエリート国立大も抽選で入学者を決める制度にして見ればよい。東大・京大卒の市場価値は失われ、学費の高い慶応・早稲田などの有名私立大学のみがエリート大学となり、私立大学の卒業生が経済社会的に高い地位を独占し、高い学費を払えない貧しい家庭の子女は地位達成の夢など見ることはできない社会となるだろう。
・・・大きく首肯したい意見です。この意見が、文部科学省の教育行政の過ちを強く糾弾しています。一つの悪き例として(筆者の考えでは)、国・公立大学の授業料の高額化です。

国立・私立大学授業料の推移(引用‥http://president.jp/articles/-/22490)
見にくいのですが、上記グラフは「国立・私立大学授業料の推移」を表したものです。グラフ一番左下隅の昭和46年(1971)当時、国立大学の入学金・授業料は、各1万円、年額12,000(月額1,000)円でした。余りに安いということで、翌年3倍増されましたが、それでも入学金・授業料は、各3万円、年額36,000(月額3,000円)。
その後、国立大学の授業料はどんどん高くなり、1990年の33万9600円から53万5800円へと約6割も上昇。「国立大学に入学してくれれば何とかなる」という親の期待は通用しない時代になってしまいました。勉学することで、未来を切り開き「世の為、人の為」に活躍を期す、若者の志を砕くような授業料の高騰は、明らかに文部行政の大失策だと考えます。大学の無償化ではなく、国・公立大学の授業料の低廉化を至急実施すべきと思うのは筆者だけでしょうか。