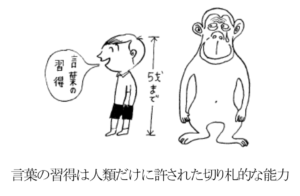羅針塾 学習塾・幼児教室では、塾生の学校の宿題は、基本的に必ず済ませることから学びが始まります。塾生の学習の基本は学校の授業です。それを抜きにして、どんなに先取り学習をしても、足が地につかない学びになってしまいます。塾生には、何よりも先ず先生の目をしっかり見ながら、良くお話を聞くように指導します。その基本が出来ている塾生は優秀です。
基本を疎かにする人は、応用が効かないのは自明です。
宿題について参考になる記事がありましたので引用してご紹介します。
みんなが忘れている「学校の宿題」の本当の目的
https://president.jp/articles/-/29905
中学棋士だった藤井聡太七段は、かつて「授業をきちんと聞いているのに、なぜ宿題をやる必要があるのですか?」と発言した。麹町中学校の工藤勇一校長は「宿題の目的は『こなすこと』ではない。わからないものを理解するのが本当の目的だ」という――。
(中略)
宿題の提出が成績に直結するのもまた事実です。
なぜ宿題がなくならないか。それは、大半の学校では子どもを評価する手段として宿題が重宝がられているからです。その背景には国の制度上の問題があります。
宿題が、出す側の問題である面も指摘しておかなければなりません。ご存じの方も多いと思いますが、公立校の成績のつけ方は相対評価から絶対評価に変わりました。相対評価の時代は「1」のつく子どもはクラスの7%、「2」が24%、「3」が38%、「4」が24%、「5」が7%と配分が明確に決まっていました。40人学級なら「5」がもらえる生徒は40×7%=2.8人なので2人だけ。つまり「5」がついたらクラスで2番以内で、昔の「オール5」とはまさに神童レベルでした。
しかし、その仕組みでは、クラス全体のレベルが高いと、勉強はできるのに相対的に評価が低くなる。そこで評価が、「絶対評価」に変わりました。ここまでは理にかなっています。しかし今度は、どのレベルを超えたら「5」を出すのか、といった判断基準が必要になります。この基準設定がとても難しいのです。
「絶対評価」になって宿題は急増した
ちなみに文科省の推奨する絶対評価の基準は以下の4項目が25%ずつの配分になっています(一部の教科は5項目)。
1 関心・意欲・態度
2 思考・判断・表現
3 技能
4 知識・理解
2~4はペーパーテストで測れます。しかし、1「関心・意欲・態度」の項目が先生にとっての曲者。一斉授業型のスタイルでは差が見えづらいのです。そのため、「関心・意欲・態度」を「宿題をやってくるかどうか」で判断する先生が急増しました。
極端な話、宿題の中身は関係なし、提出したかどうかだけを見る教員もいます。その場合も二通りいて、勉強が苦手な子に対して、宿題の提出を評価してあげたい善意タイプの先生もいますし、そもそも忙しすぎて中身まで見ていられない先生もいます。
いずれにせよ、公立学校の宿題は、文科省が評価制度を絶対評価に切り替える通達を出してから一気に増えました。すべての教科の先生が同じように悩むので、すべての教科で宿題が増えたのです。
・・・公立学校の宿題事情や背景が理解できるお話です。しかし、私立学校も似たような状況にあるのではないか、と思います。筆者の立場からすると、塾生が学校から与えられた宿題の質と量は、先生方の意図や力量を判断する物差しのようなものです。
子供達に家庭学習を自律的にするよう促す宿題ならば、自然に取り組むことができるのでしょうが。授業内容と宿題の内容がうまく連動していると学習意欲も湧く筈です。