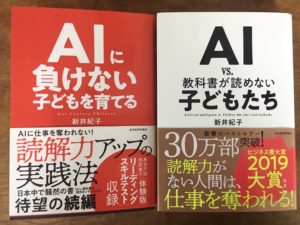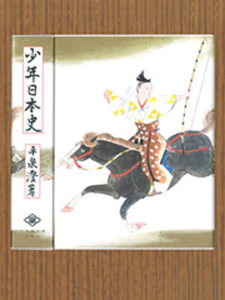長崎市議会の一般質問を御縁があって傍聴する機会がありました。限られた時間でしたが、長崎市の市長や教育委員長と質問者との質疑応答に、長崎市の教育の現場の一端が見て取れました。
所謂、ICT教育については、他の都道府県の状況を見比べながら、国の方針との整合性を図る、というような一般的な回答でした。英語教育に関しては、国立長崎大学教育学部附属小学校も含め、公立の小学校などタブレット型のツールの全員配布などはまだまだであり、現場の教員が対応できるまでの教員研修ができていない現状が浮き彫りにされています。
プログラミング教育については、小学校の先生レベルでは、全く対応できる状況ではない。つまり、児童の方がむしろ機器の活用も含め、年配の先生を凌ぐほどである、とのこと。
現実的に、文科省の旗振りほど、地方の教育界では対応できる人材教育や予算措置ができていないことが露見されたようでした。
更に、長崎市のホームページに(https://www.city.nagasaki.lg.jp/kosodate/520000/523000/p033650_d/fil/gakuchousa.pdf)「令和元年度 長崎県、全国学力・学習状況調査結果に見る長崎市の児童生徒の状況」が掲載されています。

「学力調査結果の概要」
「良好な項目」は良しとして、「課題がある項目」については、以下の課題が列挙されています。
●小学校国語では、漢字の問題や自分の考えをまとめる問題に特に課題が見られ た。中学校国語では、封筒の書き方を理解して書く問題で課題が見られた。
●小学校算数では、全国と比較して、全体的に無解答率が高い傾向が見られた。ま た、除法や単位量についての理解に課題が見られた。中学校数学では、式やグラ フなど数学的に表現されたものを事象に即して解釈することに課題が見られた。
●中学校英語では、全国平均を超えているのは 21 問中 6 問。特に「書くこと」に おいて、文法事項等を理解して、正しく文を書くことに課題がある。
また、「児童生徒質問紙調査(生活習慣や学習環境等の調査)の結果の概要」では、「課題がある項目」については、以下の課題が列挙されています。
●「難しいことでも、失敗を恐れず、挑戦する」割合は、小・中学生ともに 全国平均を下回っている。
●「家で、計画的な勉強をする」割合は、小・中学校ともに全国平均を下回 っており、特に中学校は、「2 時間以上勉強する」割合とともに、全国平 均を大きく下回っている。
●「地域の行事に参加している」割合は、小・中学校ともに全国平均を下回 っており、特に小学校は、「地域や社会をよくするために何をすべきか考 えることがある」割合とともに、全国平均を大きく下回っている。
・・・日本全国で見ると、市町村レベルで教育に熱心に取り組んでいるところとそうでないところの差が大きいと感じます。
読解力を削ぐもの2(https://rashinjyuku.com/wp/post-2202/)でご紹介した「AIに負けない子供を育てる」(新井紀子著P.186〜)には、全国学力テストの成績が高いことで知られる富山県の立山町の例を取り上げています。
つまり、富山県は秋田県や福井県と並んで、学力テストの点数が高く、教育への関心が高い県です。また、おそらく先生方も熱心で丁寧なプリント作りをし、ドリルなどもしっかり取り組ませていることでしょう。
それにも関わらず、プリント・ワークシートの多用がかえって生徒の学力に悪影響を与えているのではないか、という指摘です。
長崎市の場合、「(生活習慣や学習環境等の調査)」の結果を見ると、
●「家で、計画的な勉強をする」割合は、小・中学校ともに全国平均を下回 っており、特に中学校は、「2 時間以上勉強する」割合とともに、全国平 均を大きく下回っている。
となっており、自ら主体的に教科書をしっかりと読み、各科目の理解を高めるための努力が、家庭学習でなされていないことを示しています。これでは、学力テストの成績を上げていくどころか、一番必要な「読解力」を身につける工夫がされていないと言わざるを得ません。