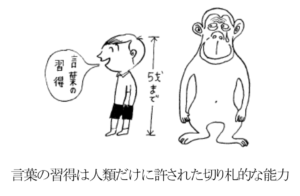羅針塾 学習塾・幼児教室では、お母様方の子育て・教育の悩みや疑問点には、出来るだけお答えしようと考えています。
過ぎ去ったことを悔やむ例えに、覆水盆に返らず(ふくすいぼんにかえらず:一度してしまったことは取り返しがつかないこと)という諺があります。子育ての最中には、気付かずに、後になって「ああすれば良かった、こうするべきだった」と。多くのお母さん方や親御さん方が思うことです(筆者自身も含め)。
筆者は、幼児期までにしておくべきだったことを、小学校高学年までは修正することが出来るのではないかと、経験的に考えます。「幼児期までにしておくべきだったこと」はズバリ母語である日本語の語彙力をつけることです。
語彙力の多寡(たか:多い少ない)は、近年の所謂核家族での会話の機会の多寡が影響していると思います。
つまり、幼児にとって家族の多さや、家族と交流する人の多さが、接触する幼児にとっては、語彙力を増やす日常的な良い機会となります。老若男女との会話を、母親の側で見たり聞いたりから始まり、挨拶をすることから、母親以外の人と会話の切っ掛けを掴むことが出来ます。
これに反し、母親以外の人々と接触することがなく、テレビなどを漠然と見る機会が多い日常では、会話が成り立たないわけですから、語彙力が増える機会が極端に少ないと言えます。(尚、何故、語彙力を増やさなければならないかは、言葉は知識を刈り入れる道具 カール・ヴィッテの教育法(https://rashinjyuku.com/wp/?s=カール・ヴィッテ)をご参照ください。)
では、生年後小学校就学までに、語彙力をつける機会を徒過(とか:徒(いたずら)に過ぎ去ってしまうこと)してしまった場合、どのようにすべきか、です。
基本的に、
●良書を数多く音読すること。
●良き文章は、丁寧に写し書きすること。
●名文(優れた文、著名な文)、漢文、短歌・俳句などを暗記するまで繰り返し読むこと。
●諺を覚えること。
・・・方法は様々あると思いますが、日本人が昔から取り組んできたやり方が一番効果的です。小学校課程の教科を学びつつ、プラスアルファ(基準となる量の、また既知の量に更に幾らか加えること)として、毎日小一時間学ぶ習慣をつけることです。毎日約一時間、365日厭(あ)かず繰り返すことで、語彙力は飛躍的についてきます。子供さんと共に「学び直し」をする姿勢が、子供さんに自立・自律する機会をも齎(もた)らします。