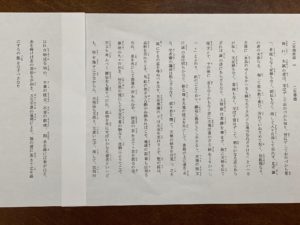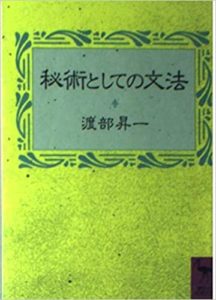幼児教室・学習塾の羅針塾では様々なご相談があります。学校給食の牛乳については、単に栄養があるからという観点から、クラス全員に何十年も供されている事に疑問を感じています。
子供さん達の学力と体調の良し悪しは密接に関連しています。牛乳を飲むことで体調不良になる子供さんには、飲ませないことが一番です。しかし、学校の現状ではアレルギーなどの医師の診断書がないと、特別扱いはできない、という方針もあるようです。
さて、
「日本人は、日本列島で採れる豊かな食材に合った身体を発達させてきた。」という「身土不二」の思想 http://blog.jog-net.jp/202011/article_2.html(国際派日本人養成講座)からの引用とご紹介です。
「身土不二」という言葉を聞かれたことがあるでしょうか。「身」すなわち人間の身体と、その人間が生まれ育った「土」つまり大地は「不二」、二つではなく一体だという思想です。
考えて見れば、私たちの身体は食べたものを分解し、そこから得られた栄養素から形成されています。そして、すべての食物はもともと、大地から育った植物か、それを食べて育った動物でした。したがって、我々の身体は食べ物を通じて大地と繋がっているのです。
この認識の上で、身土不二は、生まれた場所から歩いて行ける範囲、3里(12km)ないし4里(16km)の範囲で育った食物を食べるのが良いという思想です。
(中略)
たとえば、日本人には牛乳を飲むとお腹を壊す人が少なくありません。これは牛乳が、もともと日本の土地で生み出された飲み物ではないからです。
・・・最近の食生活の洋風化、小麦食(パン、スパゲッティなど)の増加により、また学校給食で牛乳を飲んだりする機会は増えています。それと共に、アレルギー症状(花粉症、アトピー、喘息など)も増加しています。
牛乳でお腹を壊さない方が少数派
すべての人類は、生まれてから7歳ぐらいまでは乳に含まれる乳糖(ラクトーゼ)を消化吸収する酵素(ラクターゼ)をもっています。これがないと母乳を飲んでも下痢してしまうのです。
ところが一部の人々では、7歳を過ぎるとラクターゼが消滅する事が判りました。
当初、このラクターゼ欠乏症は一部の人々とみられていました。しかし、調査が進むにつれて、じつはそれが世界の多数派で、むしろ7歳以降もラクターゼを持っている人々の方が、世界全体で20%程度の少数派であるという事実が判明しました。
・・・結局のところ、乳幼児には母親の母乳が基本であり、牛乳は母乳の不足を補う意味合いで用いるのが良い。また、離乳後の子供の成長には、牛乳は日常的に飲用するべきではないということでしょう。
また、かっての日本人にはなかった病気や疾患などの原因の一つに、古くから日本人が食してきた食べ物の比率が低下していることが挙げられます。
ヨーロッパに比べれば、日本列島の自然の豊かさは歴然としています。鹿児島に住んでいるあるアメリカ人女性は「日本の田舎の人は、食べものに囲まれて暮らしている」と言って、こう続けたそうです。
__________
海に出れば魚、貝類、海草、山へ行けば木の実、草の実、山菜。季節ごとにいろんな食べものがとれる.こんな豊かな自然はほかにないわ。まわりじゅう食べものだらけ。
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
我々の先祖は、代々、この恵まれた自然の中で得られる食べ物で生活していました。3里四方で採れる食材だけで栄養は十分でした。
上の発言に「海草」が出てきますが、最近の研究では海草を分解できる腸内細菌を持っているのは、世界の中でも日本人だけだそうです。多くの外国人は寿司は好きでも、海苔は「ブラック・ペーパー」と言って嫌います。海苔の食物繊維を消化できず、そのまま排泄してしまうのですね。日本人は海草類を食べ続けた過程で、それに適した細菌を腸内に取り込んだようです。
日本の伝統食に関して、島田博士はこう結論づけています。
__________
私たちの先祖が大事にしてきた米、粟、麦、ソバなどは、澱粉の供給源として非常に優れたものである。これで十分な炭水化物と若干の蛋白質は確保できるから、あとは蛋白質と脂肪の供給源があれば三大栄養素は大丈夫である。大豆はこの両方を満足させる食品である。日本人が穀類(米とは限らない)と大豆を核とした食生活を営んできたことは理にかなったことであった。
他にいくらかの野菜があればビタミンもミネラルも必要な量は確保できる。
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

日本の伝統食の例
・・・更に、かっての日本人と現代の日本人との比較も紹介されています。
欧米人を驚かせた、かつての日本人の体力
戦国時代に日本に上陸した最初のキリシタン宣教師フランシスコ・ザビエルは、日本人を観察して「彼らは時々魚を食膳に供し米や麦も食べるが少量である。ただし野菜や山菜は豊富だ。それでいてこの国の人達は不思議なほど達者であり、まれに高齢に達するものも多数いる」と書き残しています。
明治初年に日本で動物学・生理学を教えたアメリカ人のエドワード・モースは、人力車の「車夫たちは長休みもしないで、三十哩(今でいうおよそ50km)を殆ど継続的に走った」と驚きを語っています。[アグリコ日記]
これに比べれば、現代日本人は、かつてのご先祖様よりはるかに豊かな栄養をとっているのに、これほどの体力はありません。逆に国民病とも言われるスギ花粉症などに悩まされています。
和歌山県の山村に住む医師の報告によれば、山林労働者は大量にスギ花粉を吸っているはずなのに、スギ花粉症の人はほとんどいないとの事です。原因を調べてみると、山林労働者の朝食は米飯が95%であるのに、スギ花粉症の人々は60%がパン食でした。そこでスギ花粉症の人々の朝食をパンから米飯に変えると、ほとんどの人の症状が楽になったそうです。
この原因として、麦は米に比べるとほとんどが輸入のため収穫したあとに農薬をかける(ポストハーベスト農薬)ので残留農薬が多い、パンは米に比べ食品添加物が多い、などが考えられています。
・・・このような話は、様々なところで経験的に語られることが多いようです。
「心身ともに健やかで賢い子」が親御さんにとっての願いです。
その為にも、食生活の再確認はとても大事なことです。