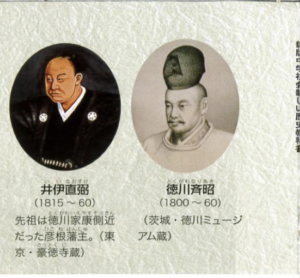長崎市五島町にある羅針塾 学習塾・幼児教室 https://rashinjyuku.com/wp では、春期講習も最終日となり、塾生も一所懸命に学習やお楽しみに取り組みました。
「ちょっとした勉強のコツ」外山滋比古著(みくに出版)という読んで楽しい著作があります。勉強の骨(物事の核心)を掴むか否か、は長い人生で考えると、大きな差を生み出す素です。その中の一節から引用してご紹介します。
朝飯前
かってある人が、ヨーロッパからオーストラリアへ移住した。ヨーロッパには長く厳しい冬があるけれども、オーストラリアでは常夏のように年中、何か花が咲いている。それを見てこの移住者は養蜂業を始めようと思いついた。こんなに花があるのなら、さぞ蜜が沢山取れるだろうと考えたのである。
早速ヨーロッパから優秀な蜜蜂を輸入して、仕事は始まった。最初の年は大成功だったが、二年目には収穫が激減、それから年々大きく減り続け、やがてほとんど蜜を集めなくなってしまった。おかしいと思って調べて貰ったら、いつも花があるからだという意外なことがわかった。ヨーロッパで働き蜂といわれるほどに勤勉であったのは、花のなくなる冬があるからだったのである。年中花のある恵まれたところに移って、蜂はハングリーでなくなってしまったらしい。
それは蜂の話、人間は別だ、とは言い切れないようである。人間も概して、厳しい環境におかれた方がよく働く。欧米の人たちは、雪の降る国でないと、文化、文明は栄えないと信じているようだ。寒いところの人間は、温暖なところで生活する人に比べると、おしなべて勤勉で努力する。それがやがて社会の繁栄に結び付く、そう考えるのである。悪条件のもとでは、ハングリーにならずにはいられない。ハングリーならよく働くというわけだ。
一人一人についても同じことが言える。いまアメリカで最も優秀な学生は、ベトナムやカンボジアからボート・ピープルとしてアメリカへ渡った 難民家族の子女である、と言われる。ハーヴァード、イエール、プリンストンなどの名門大学へすいすい入学する。ハーヴァードなどでは定員の二十パーセントを超えて問題になったほど。
ベトナム、カンボジアからの難民が秀才、才媛だけを連れて行ったわけではあるまい。物心ともに不自由、不如意な環境で育ったために、石に齧りついても、といった勉強をした。ハングリーだったからこそ、目覚ましく学力を伸ばしたのである。
誰でも難民のような境遇になれるわけではなく、そういったハングリーな生き方をするのも困難である。しかし、特に厳しい暮らし方をするのではなくても、腹をすかせていれば、おのずとハングリーになることができる。仕事をしようと思ったら、満腹、飽食はいけない。
テレビやラジオのアナウンサーは、放送する何時間も前から食べ物を口に入れない。胃にものが入っていると、言い間違い、読み違いが多くなる。神経を張り詰めた仕事をするに空腹でなくてはいけないのを経験で知っている。ハングリーの状態が良いのである。逆に言うなら、ものを食べたあとは、精神を集中させることは避けるのが賢明だということになる。昔の人も、親が死んでも食休み、と言った。
また動物の話になるが、ライオンに芸、例えば、火の輪をくぐらせるというようなことを仕込むのは、空腹時に限るという。火の輪の向こうに肉の切れ端をぶら下げておく。くぐったらそれを与える。腹をすかせたライオンは肉切れが欲しくて火の輪をくぐる。満腹のライオンは首を縦に振ることすら大義がる。
学校の授業で、昼の食事の後は居眠りが多い。これは体が食休みを要求している証拠である。こういう時間の勉強はあまり効果がない。
ハングリーであるには、1日の早い時間ほどよいようだ。一番よいのは朝ということになる。頭の仕事にとって、朝は金の時間である。ただし食事をするとたちまち鉄の時間になる。昼食前は銀の時間。食後は鉛の時間になるが、夕方の腹の空いているときはまた銀の時間がやってくる。夕食後は鉛の時間を通りこして、夜の十時以後ともなれば石の時間である。夜型などと称してそんな時間になってから頭を使っていれば、石頭になっても不思議ではなかろう。
つまり、頭を使うのは、朝、しかも食事の前がベストだということになる。その時間なら心身共に快適でハングリーな状態にある。ここで朝飯前ということばがあるのを思い合わせる。
この言葉は、今では、朝食を食べる前に仕上げられる仕事というところから、ごく簡単なことの意味になっている。しかし、もとの心は、朝、ものを食べる前は心身爽快・きわめて能率が良いから、たとえ厄介なことでもさっさと片付けられる、というところから出ているに違いない。
前の晩に、どうしてもうまくいかなかったことが、一夜明けてから、朝食前にしてみると、あっけないほど簡単にできてしまう。そういうことを経験した人は少なくないはずである。
朝食前の時間は、よほど早起きをしない限り、ほんのわずかしかとれない。それを伸ばす工夫として、私はかって、朝食をおくらせ、昼食といっしょにすることを考えて実行した。これだと午前中がすべて朝食前になる。医者は健康のために朝食をとれと教えるが、頭をうまく使うのに朝昼の食事を合併させるのは名案である。英語のブランチは朝食と昼食を兼ねた食事である。朝食前の時間を大切にする人たちが考えたことに違いない。
・・・学習の効率を上げたいと考える人ならば、必ず考えたであろうことの一つが、食事と眠気のコントロールではないでしょうか。筆者の母がよく問わず語りで言っていた言葉が、「腹の皮が突っ張れば、目の皮が緩む」、つまりお腹いっぱい食べると、瞼が重くなって眠くなる、ということです。一般に、若いときはいつまででも眠っていたいというほどよく寝ます。勉学に励まないといけない試験前などは、さあ頑張る為に腹ごしらえ、と思うと必ず眠気を催してしまった苦い経験を持つ人は多いと思います。育ち盛りの時期に、空腹で学習に取り組むというのは至難の技ですね。