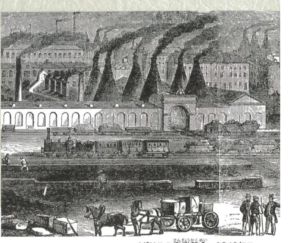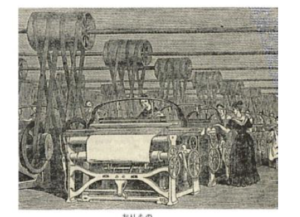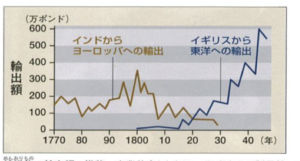長崎市五島町にある羅針塾 学習塾・幼児教室 https://rashinjyuku.com/wp では、塾生がしなければならない学校の宿題から始めます。学校の授業が、学びの根本と考えるからです。それぞれの学校の先生方が、一所懸命に準備して下さった授業のメッセージが宿題に託されています。
さて、「学校はそもそも何をする所か」と、様々な思いを込めた記事が目に入りました。産経新聞201.2.7
http://www.sankei.com/life/news/180207/lif1802070007-n1.htmlからの引用です。
学校はそもそも何をする所か 「学びを軽んじる教育機関」にさせてはならない 教育評論家・石井昌浩
鎌倉初期・足利学校創立のときから、学校はひたすら学ぶところだった。
学校の機能には多様なものがあるが、いかなる時代にあっても学ぶことがその中核だった。
時が移り、今では、部活動が教師の長時間労働を招き、教師を疲弊させる元凶のように言われている。しかし、これは「木を見て森を見ない」批判ではないかと思う。
たしかに、OECDの調査では、日本の小・中学校の教師の勤務時間は対象国で最長である。しかも授業に使う時間が対象国の平均を下回る一方、部活動など課外活動の指導の時間が際立って多い。文部科学省の調査でも、長時間勤務が浮き彫りになっている。過労死の危険が高まるとされる月平均80時間を超す残業をする公立学校の教師が中学校で約6割、小学校で約3割に達している。
ここ数十年、学校、特に公立学校が困難に陥っている最大の原因は、学校が伝統として守ってきた教育機能が総体として衰えたことにあると思う。これは部活動を工夫して時間を短縮すれば解決するほど単純な話ではない。部活動の在り方を含めて、学校が抱える問題全般が噴き出した結果とみるべきだ。
ところで、子供たちが学校で学ぶ内容は学習指導要領で定められていることは大方の保護者が知っている。指導要領を基にして教科書がつくられ、子供たちが、何を、いつ、どのくらい学ぶかを決めているのも指導要領である。指導要領に従い学校がカリキュラムとか時間割といわれる教育課程を定める仕組みになっている。
ちなみに、平成29年3月に改定された学習指導要領は、部活動について、学校運営上の留意事項として、概略次のように説明している。「教育課程外の学校教育活動と教育課程の関連が図られるように留意するものとする。特に、生徒の自主的、自発的な参加により行われる部活動については、スポーツや文化、科学等に親しませ、学習意欲の向上や責任感、連帯感の涵養(かんよう)等、学校教育が目指す資質・能力の育成に資するものであり、学校教育の一環として、教育課程との関連が図られるよう留意すること」
この記述で明らかなように、部活動は正規の教育課程には位置づけられていない。しかし、学校教育の一環でもあるため、教育課程との関連にも留意するように念押しされている。丁寧な書きぶりだが、分かるようで分からない、あいまいで複雑な言い回しである。
ここで、子供たちを取り巻く教育環境を見渡してみると、学校が教科指導の力を失った部分を、学校外教育機関である塾や進学教室が補っている事実が明らかになる。学校教育の根幹である教科を教える機能の「外注化」が進んだ結果として、学校は次第に、部活動や生活指導に重点を移さざるを得なくなってきているのだ。
見逃せないのが近年の大学入試の在り方の変化が、学校の部活動重視の傾向に拍車をかけていることだ。「部活がウリ」になるからだ。私立大学の入試の45%がAO入試と推薦である。最近は私立だけでなく国公立大学でもAO入試・推薦方式を導入する動きが加速している。
教師の本当の値打ちは日常の教科指導の場面で試される。多くの教師は十分に時間をかけて準備した授業で子供たちに接したいと、心から願っている。
授業以前に疲れ果てて、授業準備にあてるゆとりのない学校など本末転倒だ。学舎(まなびや)の伝統を守り続けてきた日本の学校を「学びを軽んじる教育機関」にさせてはならない。
・・・学校の先生方の悲鳴を代弁しているかのような論説です。
筆者は、塾を主宰していますが、公立・私立の学校が本来の教育を純粋に追求出来ていれば、学校の授業を補完するような、また受験をする為だけの塾は、本来不要と考えます。要は、これからの日本を支える子供達を、大人が如何に支え、その力を伸ばしてあげることができるか、です。学校の先生方も悩んでおられることでしょう。それらの先生方の力を発揮出来る様にすることが、これからの日本の教育を良き方向へ導いていくことになります。