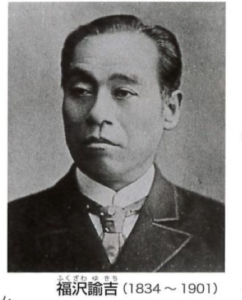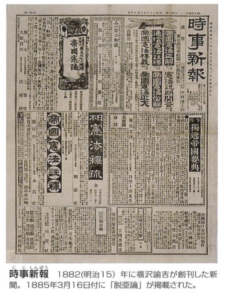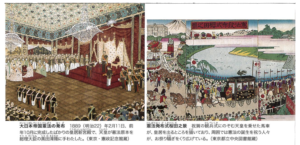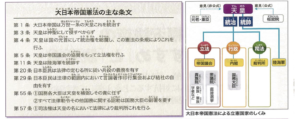長崎市五島町にある羅針塾 学習塾・幼児教室 https://rashinjyuku.com/wp では、日本人としてしっかり母国語を学ぶことが、結果として英語や仏蘭西語、西班牙語などの外国語も学ぶことができると考えています。例えば、漢字の練習。小学校へ進学して、どれほどの漢字を練習しているかによって、その後の語彙力の差になって表れてきます。漢字を継続して練習する力は(筆者が考えるに)、そのまま英語の単語力や語彙に直結しているように思います。つまり、小学校高学年の英語や、中学校の英語の授業で、どれほど英単語の練習をしているかを考えると、非常に心もとないのが現状です。それは、英語の授業時間の中で、単語を練習させたくても時間が取れないことや、そもそも筆記体で英単語を書かせないことが原因のように考えます。小学校の時に、ひたすら漢字を練習していた経験からすると、英単語をひたすら練習する機会は圧倒的に少ないと感じておられる親御さんが多いのではないでしょうか。特に、いわゆる「ゆとり世代」の親御さんは、愚直に漢字や、英単語を繰り返した経験が少ない世代のように思います。無論、その時代を過ごした子供達には責任があるわけではなく、その時代の教育を担ってきた立場の人たちの責任、と言えないか、です。
結果、何事も素直に暗記することを習慣付けることができなくなってしまう。
幼い時から、暗記する癖をつけて仕舞えば、覚えようと意識しなくても、何回か音読することで覚えることができます。自然に頭に入って行く経路を作ることが非常に大事です。
漢字にしても、英単語などの外国語の単語にしろ、覚えるのに無理のないシステムを幼児期に構築することが肝要ではないかと考えます。
さて、「英語と歴史を同時に学ぶ」シリーズです。
改めて、少し歴史を遡ってみようと思います。http://www.sdh-fact.com/CL02_2/Chapter%204%20Section%201,%202.pdf

Chapter 4: Modern Japan and the World (Part 1) – From the Final Years of the Edo Shogunate to the End of the Meiji Period
Section 1 – The encroachment of the Western powers in Asia
Topic 47 – Industrial and people’s revolutions
What events led to the birth of Europe’s modern nations?
People’s revolutions
The one hundred years between the late-seventeenth and late-eighteenth centuries saw the transformation of Europe’s political landscape. In Great Britain, the king and the parliament had long squabbled over political and religious issues. When conflict over religious policies intensified in 1688, parliament invited a new king from the Netherlands to take the throne. The new king took power without bloodshed and sent the old king into exile. This event, known as the Glorious Revolution, consolidated the parliamentary system and turned Britain into a constitutional monarchy.1
*1=In a constitutional monarchy, the powers of the monarch are limited by the constitution and representatives chosen by the citizens run the country’s government.
Great Britain’s American colonies increasingly resisted the political repression and heavy taxation imposed by their king, and finally launched an armed rebellion to achieve independence. The rebels released the Declaration of Independence in 1776, and later enacted the Constitution of the United States, establishing a new nation with a political system based on a separation of powers.2
*2=Under a separation of powers, the powers of the government are split into three independent branches: legislative, executive, and judicial.
第4章 近代の日本と世界(1) 幕末から明治時代
第1節 欧米諸国のアジア進出
47 市民革命と産業革命
ヨーロッパの近代国民国家はどのようにして生まれたのだろうか。
市民革命
17世紀後半からの約100年間に、ヨーロッパの政治に新しい動きが起こった。イギリスでは、政治や宗教の対立から、国王と議会の間で長い抗争が続いていた。1688年、宗教政策などを巡って対立が激化し、議会はオランダから新しい国王を迎えたが、旧国王は外国に亡命し、流血を見ることはなかった。これを名誉革命という。これによって、議会制度の基礎が固められ、イギリスは立憲君主制*1の国家となった。
*1 憲法によって君主の権限を制限し、国民が選んだ代表が政治を運営する国家の仕組み。
イギリスの植民地だったアメリカは、本国の国王から課せられた重税と弾圧に抗議して、武器を持って独立戦争を戦った。1776年、アメリカは独立宣言を発表、その後、合衆国憲法を制定し、三権分立*2の国家体制を確立した。
*2 国家の権力を、立法・司法・行政の三つに分け、それぞれ独立させる仕組み。

イギリスの名誉革命 アメリカの独立宣言
In 1789, an angry mob of Parisian citizens, who groaned under oppressively heavy taxes, stormed the Bastille Prison, an incident that sparked numerous rural and urban revolts throughout France against the king and the aristocracy. This was the start of the French Revolution. The revolutionary forces abolished class privileges and drew up the Declaration of the Rights of Man and of the Citizen, enshrining the principles of liberty and equality. The revolutionaries soon turned blood-thirsty and beheaded the king and queen for refusing to abide by their program. It has been estimated that 700,000 people were killed amid the “reign of terror,” as the period of chaos during the French Revolution is called. Fearing the spread of the revolution, France’s neighbors intervened. Napoleon Bonaparte seized control of France to confront this threat and, for a time, he dominated most of continental Europe. As a result, the ideals of the French Revolution spread across Europe. Because these political revolutions gave rise to modern nation-states aspiring to the legal equality of all citizens, they are called people’s revolutions.
イギリスの名誉革命 アメリカ独立宣言
1789年、重税に苦しむパリ市民がバスチーユ牢獄を襲撃したのがきっかけとなり、国王や貴族に対する都市市民や農民の反乱が各地で起こった。フランス革命の始まりである。革命勢力は、自分たちの主張に従おうとしない国王・王妃を処刑するなど過激化していった。革命の混乱の中で70万人の国民が殺されたと言われている。フランスの周辺諸国は革命の広がりを恐れて干渉した。それに対抗してナポレオンが権力を握り、ヨーロッパ諸国を一次的に支配した。これによってフランス革命の精神がヨーロッパに広がった。これらの政治的改革は、人々が平等な市民(国民)として活動する社会を目指して近代国民国家を生み出したので、市民革命と呼ばれています。
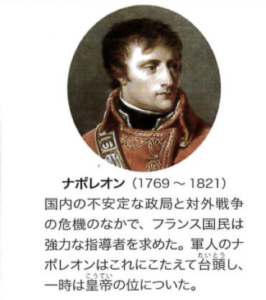
・・・筆者は、小・中・高とこの時代の歴史を繰り返し学びながら、なんとなく違和感があったのを覚えています。何故なら、欧米の変革の歴史が「革命」という名の国民を「粛清」する嵐のように思えたからです。つまり、中世の基督教の旧教と新教との長年に渡る、言わば内輪の争いによって膨大な数の民への殺戮を繰り返した歴史のままの様に思えるからです。少なくとも、民族的にも宗教的にも、互いが違和感のない民同士の日本は、長い歴史の中で、自国民による大量殺戮の歴史はありません。二千年を超える歴史を持つ日本は、明らかに世界の国々とは、違う歴史の流れがあるかの様です。