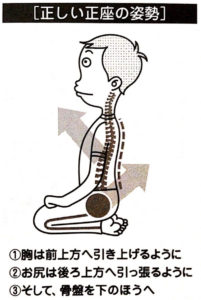長崎市五島町にある羅針塾 学習塾・幼児教室 https://rashinjyuku.com/wp では、塾生がドアを開けて入ってくるその様と挨拶をみて、体調の良し悪しを判断します。元気に入って来るか否か、声の大きさなどに、その塾生の心身の調子が表れます。それをみて臨機応変に、為すべきことを指示します。
さて、以下の記事が目にとまりました。
「英語に関する意識調査」を未成年・成人計10,000名に調査 ~英語の活用意欲は成人より未成年が高い傾向に~https://gmo-research.jp/pressroom/survey/voluntary-survey-20170929
調査の趣旨は、
「昨今の日本では、グローバル化への対応が急がれており、 世界で活躍する人材を育成するためにも、国際共通語である英語教育のニーズが高まっています。小学校における英語教育も本格化しており、2008年に小学5、6年生を対象に「外国語活動」が導入され、2011年には必修化されました。また2020年までには、小学3年生から英語教育が必修化し、小学5年生以上は「教科」として英語が導入される予定となっており、今後さらに英語教育の改革・充実が進んでいくと考えられています。一方、企業においても、英語の公用語化や英語学習の推進などの取り組みが進んでいます。
今回GMOリサーチは、こうした英語力教育の高まりを受けて、実際に英語教育に触れてきた 15歳~19歳の未成年男女と、20歳~59歳の成人男女の英語に対する意識を探り、その実態を比較するべくアンケート調査を実施いたしました。」・・・とのこと。
詳細は、上記のサイトをご覧いただきたいのですが、「英語に苦手意識を感じ始めた時期」、「英語を苦手と感じる理由」も興味深いものです。
<苦手意識を感じ始めた時期>
「苦手意識がある」と回答した人に、英語を苦手と感じるようになった時期を尋ねたところ、未成年・成人ともに「中学1年(未成年:25.8%、成人:33.3%)」が1位となり、本格的に英語を学び始める時期に苦手意識が芽生えることが多いことがわかった。また、未成年は「中学2年」(20.9%)、「高校1年」(14.3%)と続き、成人は「社会に出てから」(18.8%)、「高校1年」(12.9%)と続いた。このことから、未成年・成人に共通して、より複雑な英文法や長文読解を教わり始める「高校1年」に、苦手意識が芽生える第2の波が訪れていることがうかがえる。さらに、成人は「社会に出てから」が約2割にのぼり2位となっていることから、苦手意識を感じながらも、ビジネスで英語を使わざるを得ない場面に直面している人も多いことが垣間見える結果となった。
<英語を苦手と感じる理由>
英語を苦手と感じる理由については、未成年・成人ともに「英語を使う機会がない(未成年:69.6%、成人:89.5%)」が1位となった。特に成人は約9割もの回答を集め突出しており、利用シーンの少なさが英語の苦手意識につながっていることがうかがえる。また、未成年は「文法がわからない」(66.1%)、「単語が覚えられない」(54.2%)、「英文を読み解くことが難しい」(50.4%)が過半数にのぼり、単語や文法に関する項目に回答が集まる結果となった。一方、成人は「聞き取りができない」(62.6%)、「文法がわからない」(52.8%)、「発音が難しい(48.7%)」と続き、未成年と比べて、聞き取りや発音といった英会話に関する項目で苦手意識を感じている人が多いことがわかった。
必要性は感じながらも、「未成年・成人ともに「英語を使う機会がない(未成年:69.6%、成人:89.5%)」 特に成人は約9割もの回答を集め突出しており、利用シーンの少なさが英語の苦手意識につながっている、などは当然の結果と思います。日本人社会において、ほとんどが日本人に囲まれていて、英語を使う機会がないにも関わらず、英語を学ばなければならないという強迫観念だけが突出しているかのようです。
更に、
<現在英語を活かしている場面>
また、現在英語を活かしている場面については、未成年は「学校やスクールで学ぶ」(42.0%)が一位となった。成人については「特になし」(67.3%)が約7割と、日常的に英語を活用していないことが改めて浮き彫りとなった。
<今後英語を活かしたい場面>
今後英語を活かしたい場面については、未成年は「海外旅行」(42.9%)が最多となり、その他「英語の曲を聴く」(27.5%)、「外国人の友人との交流」(26.5%)、「英語の映画やドラマを字幕なしで見る」(24.7%)などにも2割超の回答が集まった。一方で成人については、「特になし」(55.5%)が過半数、その他の項目も未成年を下回っており、成人は未成年よりも英語の活用意欲が低い結果となった。
「現在英語を活かしている場面」「今後英語を活かしたい場面」のアンケートを見ても、英語を公用語にしている国や生き抜くために英語が必須である国の人々と比較して、日本に住む日本人には、必要性や緊急性がない中で英語学ぶことは動機が不十分であるように思います。
生き抜くために必須の英語とそうではない日本の環境で学ぶ英語では、取り組む姿勢が違います。寧ろ、本当に英語を用いなければならない機会に備えて、日本語(国語)力を磨き、「読む」「聞く」「話す」「書く」という4技能が日本語で十二分に発揮できるようすべきではないかと思う昨今です。