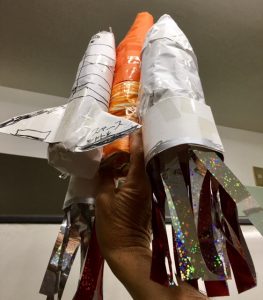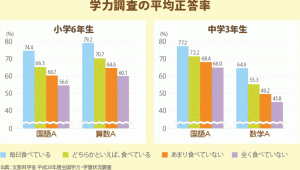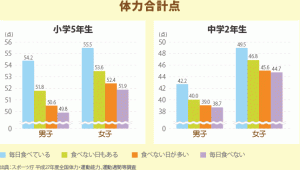長崎市五島町にある羅針塾 学習塾・幼児教室では、夏休み(正式名称は「夏季休業」と言いますが)は、学校の業務ないし授業が休みということであり、学力向上には休みはない、と考えています。
その為には、湿気も多い日本の夏は、冷たいものを食べてお腹を壊したり、クーラーと常温との温度差で体調を崩すことが多いので要注意です。
何より、規則正しい生活を送るためには、早寝・早起き、健康的な食生活は欠かせません。
学力向上の必須条件は、それらを維持することから始まります。
「夏休み中も正しい食生活は重要!」(産経新聞2017.7.19)からの引用です。
http://www.sankei.com/life/news/170719/lif1707190023-n1.html
小学校ではほとんど、中学校でも多くの学校に、給食があります。学校給食は、栄養教諭・学校栄養職員をはじめとした人たちの努力で、バランスのよい食事が日々提供されています。しかし学校給食も、重要な教育の一環です。食育は、現行の学習指導要領でも重視されていますし、次期指導要領でも更に充実されます。
「早寝早起き朝ごはん」の標語で啓蒙活動をしているサイト(「早寝早起き朝ごはん「全国協議会http://www.hayanehayaoki.jp)もあります。そこからの引用です。
子供たちの健やかな成長には、「早寝早起き朝ごはん」をはじめとした規則正しい生活習慣が大切です。近年、子供たちの生活習慣の乱れが学習意欲、体力、気力の低下の要因の一つとして指摘されています。
また更に、
「朝食の摂取と学力・体力の関係」では、朝食を毎日食べている子供の方が、学力調査の平均正答率や体力合計点が高い傾向にある、ということも指摘しています。
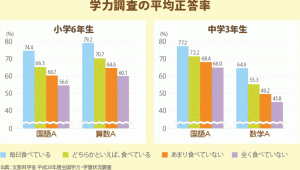
学力調査の平均正答率
明らかに毎日食べている子供たちが国語、算数・数学の正答率が高い傾向にあります。
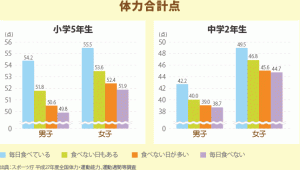
体力合計点
スポーツ庁平成27年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査の結果も、毎日食べている子供たちが良い値を示しています。
また、睡眠の効果について
従来から「寝る子は育つ」と言われていますが、睡眠には心身の疲労を回復させる働きのほかに、脳や体を成長させる働きがあります。
脳には海馬という知識の工場があり、睡眠中に活性化し、昼間経験したことを何度も再生して確かめ、知識として蓄積しています。この海馬の働きを助け、子供の成長に欠かせない脳内物質であるメラトニン(暗くなると分泌され、体温を下げて眠りを誘う働き)と成長ホルモン(寝入ってすぐの深い睡眠時に分泌され、脳、骨、筋肉の成長を促す働き)は眠っている間に活発に分泌されます。眠る時間が遅くなると、これらの脳内物質の分泌に影響を与えてしまうので、午後9時ごろには就寝させるように心がけましょう。
朝の光の効果
朝の光を浴びると、脳の覚醒を促す脳内ホルモンであるセロトニンが活発に分泌されます。その結果、頭がスッキリと目覚め、集中力があがります。また、自律神経が副交感神経から交感神経に切り替わり、活動に適した体になります。
セロトニン分泌は、夜寝ているときにはなく、朝起きると始まります。セロトニンの分泌を増やすには、陽の光を浴びて体を動かすことや、しっかりと噛んで朝ごはんを食べること等が効果的です。
一方、陽が沈むと睡眠を促すホルモンであるメラトニンが合成されます。このメラトニンは、セロトニンを材料にしているので、昼にセロトニン分泌を増やすような活動をすることが大切になってきます。
このように朝の光を浴びて、昼に活動を行うことにより、夜にはメラトニンがたっぷりと合成され、よく眠ることができるようになります。
朝食の効果
脳のエネルギー源はブドウ糖です。ブドウ糖は体内に大量に蓄えておくことができず、すぐに不足してしまいます。また、私たちの体は寝ている間もエネルギーを使っているので、朝にはエネルギーや必要な栄養素が少なくなっています。つまり、朝起きたときは脳も体もエネルギーが不足した状態なのです。そのため、朝食でブドウ糖をはじめとする様々な栄養素を補給し、午前中からしっかり活動できる状態を作ることが大切です。
しかし、ドリンクやゼリーなどで栄養を摂りさえすればいいというわけではありません。朝食でもう一つ大切なことは『よく噛んで食べること』です。『噛むこと』で脳が覚醒し活発になります。また、口に食べ物が入り、胃に送られてくると腸や大腸が動き始め、内臓も目覚めます。それが朝の排便習慣にもつながります。
昔から「早寝早起きは三文の徳」というように、日本人の先人たちは多くの効用があることに気づいていたのですね。