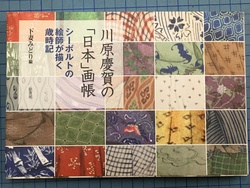岩波文庫版の「和俗童子訓」に、
「父たり傅育者*たるものの注意」という注釈のついた項目があります。
*傅育(人に仕えて守り、世話をすること)
両親や子育てに関わる人は、子供が幼い時に、言行(言葉と行い)に対してあまり厳しいことを言うのは良くないのではないか、という漠然とした思いがありますが、貝原益軒先生はその誤りについて厳として指摘されます。
また、平安時代には既に語り継がれ記されてきた『実語教』なども、時機を逃さず教え諭すことの重要性を記しています。
天文十八年(1549)に日本にキリスト教を伝えたザビエルやそれに続く宣教師達も、当時の日本人の老若男女を問わない識字率の高さや倫理観の高さに驚嘆した記録が残されています。
余談ですが、キリスト教を布教する際に、日本人が様々に宣教師に質問するので閉口し、他の国と違ってキリスト教を布教することは簡単にはいかない、ということも記録されているほどです。
つまり、当時の日本の一般庶民が、
「キリストの教えを信じれば私たちは救われるとしても、既に亡くなった先祖はその教えを受けることができないので救われないことになるが、如何」
と問い、ザビエル達宣教師が答えに窮したとの逸話が残されています。
さて、
貝原益軒先生の「和俗童子訓」。
江戸時代の子を持つ親に向けて分かり易く説いています。
貝原益軒 和俗童子訓 巻第一 総論上
<読み下し文>
小児の時より、年(とし)長ずるにいたるまで、父となり、かしづきとなる者、子のすきこのむ事ごとに心をつけて、選びて、このみにまかすべからず。
このむ所に打ちまかせて、よしあしをゑらばざれば、多くは悪しきすぢに入(いり)て、後(のち)はくせとなる。
一たび悪しき方にうつりては、とりかへして、善き方に移らず、いまし(禁)めてもあらたまらず、一生の間、やみがたし。
故にいまだそまざる内に、早くいましむべし。
ゆだんして、其子のこのむ所にまかすべからず。
ことに高家(こうけ)の子は、物ごとゆたかに、自由なるゆへに、このむかたに心早くうつりやすくして、おぼれやすし。
はやくいまし(戒)めざれば、後に染(そ)み入(いり)ては、いさ(諫)めがたく、立ちかへりがたし。
又、あしからざる事も、すぐれてふかくこのむ事は、必(ず)害となる。
故に子をそだつるには、ゆだんして其このみにまかすべからず。
早くいましむべし。
おろそかにすべからず。
予(あらかじめ)するを先(せん)とするは此(この)故なり。
<現代語訳>
・・・小児の時より年長にいたるまで、父やその子に仕えて守り世話をする人は、子供の心が惹きつけられ好むことがある度にその心を慮って、子供の選り好みに任せてはならない。
好むところに完全にまかせて、善悪を分別しなければ、そのほとんどは悪い方面に入って、その後はくせ(正しくない、真っ当ではないこと)となる。
一度悪い方向へ移ってしまうと、取り替えをして善い方向へは移らず、禁じても改まらず、一生の間止めることは困難である。
故に(こういうわけで)、未だ染まってしまわない内に、早く戒める(誤りのないように、前もって注意する)べきである。
油断(気を緩め、注意を怠ること)して、その子供の好むところに委ね(一切を任せること)てはいけない。
とくに高家(由緒正しい家、名門)の子供は、物資(生活の支えとなる衣料や食料など)等も豊かであり、自由に用いることができるために、自分の好みで心変わりや心移り(好みが他に変わること)しやすく、溺れ(あることに夢中になって心を奪われること)やすい。
早く戒めず、悪いことが染み付いてしまった後になっては、諌め(禁止、制止すること)ようとしても困難になり、元に立ち戻ることができなくなる。
また、必ずしも悪いことではないことも、とりわけて深く好むことは、必ず有害になる。
故に、子育てをする際には、油断(気を緩め注意を怠ること)してその子供の好みに任せてはいけない。
早く戒めなければならない。
おろそかに(等閑(なおざり)、いい加減な様)してはならない。
予め(将来の事態に先立って、ある物事を行う様)すべきことを先になすのはこの理由からである。
**********************
子供さんは勿論、人を叱ることは大変に難しいことです。
しかし、その子の為に、その人の為にと信ずるならば、敢えて言うべき時があります。
子供さんにとって唯一無二の親だからこそ、厳しく愛情を持って叱るべきです。
「叱る」と「怒る」は、全く違う言葉ですが、混同して用いられている言葉です。
「叱る」は、目下の者の言動に対し、欠点や誤りを強く咎めて戒めること。同じ過失を起こさないように、過失を戒めること、です。
「怒る」は、「起こる」(ある感情や欲望が心の中に生ずる)と同源で、感情が高まるの意味から腹を立てること、です。
親御さん方は、その違いを認識して、叱るべき時にはしっかり子供さんを叱ってあげてください。