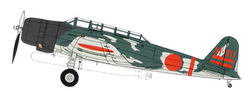筆者は4月に伊勢神宮に参拝。
限られた時間でしたが、清明な伊勢の森に荘重な社殿が佇み、不思議な思いを持ちつつ参拝しました。

伊勢神宮内宮
外国人が日本文化の素晴らしさを日本人に伝えた例として、ドイツの建築家、都市計画家であったブルーノ・タウトがいます。
数寄屋造りの中にモダニズム建築に通じる近代性があることを評価し、日本人建築家に伝統と近代という問題について大きな影響を与えたとされています。
さて、教科書に載らない歴史上の人物の再掲(加筆)です。
***************************

ブルーノ・タウト
「元気のでる歴史人物講座」日本政策研究センター主任研究員 岡田幹彦氏の産經新聞記事(H.21.1.14)からの引用です。
■日本を熱愛した建築家
日本文化の価値を日本人に目覚めさせた外国人にドイツの世界的建築家、ブルーノ・タウトがいる。
日本人は日本文化が、これまで世界からいかに高い評価を受けてきたかあまり知らない。
西洋の芸術家にとり日本の文化芸術は常に憧憬(しょうけい)の的であった。昭和8年、夫人と共に来日したタウトほどわが国の木造建築を絶賛し、世界的評価を与えた人はいない。
彼は日本建築の最高峰として伊勢神宮をあげ、「世界建築の聖祠」とたたえている。もう一つが桂離宮である。
庭園美と不離一体となった桂離宮にタウトは伊勢神宮以上の感銘を受け日本美の極致をみた。
「私たちは今こそ真の日本をよく知り得たと思った。すぐれた芸術品に接するとき、涙はおのずから眼に溢れる。まことに桂離宮はおよそ文化を有する世界に冠絶した唯一の奇蹟である。パルテノンよりもゴシックの大聖堂あるいは伊勢神宮におけるよりも、ここにははるかに著しく“永遠の美”が開顕せられている」明治以降、日本人はあまりにも自国の文化、芸術を軽視し、やたら外国のそれを崇拝してきた。
しかし、建築のみならず芸術、文化全般にわたり、わが国ほどすぐれたものを持つ国はどこにもない。
日本を熱愛したタウトは日本文化が今後の世界において重大な貢献をし、世界が日本の文化、文明を渇仰する日が必ず到来することを確信してやまなかった。
神社・仏閣など、長い年月を経て現存している建物には、不思議な魅力があります。
新築時には絢爛豪華であっても、年を経て木と土壁のモノ・トーンの静謐さが人を魅了します。
筆者は学生時代に桂離宮に行きたくてたまりませんでしたが、公開日との日程が合わずにご縁がないまま現在に至っています。是非参観したい建物の筆頭です。
ブルーノ・タウトとは (さらに…)