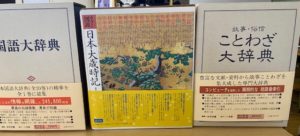小学校受験はどのようにしたら合格しますか。
どんなことを勉強すればいいのですか。
カリキュラムを教えてください。
お母様達からの質問です。
羅針塾では
「子供さんの成長をみて」と話します。
小学校受験には子供の成長を左右するものに
お母様の力が一番必要だと考えているからです。
小学校に上がるまでに必要なことは沢山あります。
しかし、放っておいても育ちません。
与えるべくして与える。です。
一人一人の成長の差があります。
型には嵌める事はできません。
けれど、自分勝手すぎるのもいけないのです。
このバランスを一人一人に理解させていく。
とても大事な事だと思います。
この子はできて、家はできない。
と、どうしても比べがち。
病気でない限り、大人になっても
おねしょをする子はいないし
食べることができない子もいませんよ。
「やろうね」「教えてね」と促すことと
辛抱強く待つことも大事です。
身体と心の成長が必要です。と伝えます。
「ハキハキ!元気!賢い子」
一つ一つ、問われていることに
考え、導く力。
理解し伝える力。
毎日の学びの中にあります。
階段を登ったり降りたり・・・
一つ一つの小さな挑戦が幼児期には必要です。
羅針塾では
手を動かし、観て、聞いて、考え、伝える。
幼児期に大事なことを丁寧に取り組んでいます。
これが、勉強することなんだ。
なあんだ。楽しいね!と言ってもらえるように。
そして、御家族が希望する小学校にトップで
入学できるように。
導いていきます。