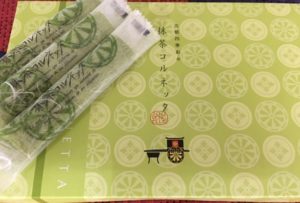国語教育の基本は、子供の成長に応じ正しい発音と発声で書物を音読することです。
形態としては、単独でする音読(声を出して読むこと)、師匠と弟子のように相対してする素読(意味を考えないで、文字だけをを声を出して読むこと)、同じ目的を持つ複数の人がする輪読(数人が一冊の本を代わる代わる読んで解釈し意見を交わすこと)や会読(数人が一箇所に集まって同一の本を読み、研究や討論をすること)などがあります。
管見では、音読の為の書物は、文章にリズムがあり、歯切れの良いものがお勧めです。文章の難易や内容は、子供の現在の理解度に合わせるのではなく、将来自ら学ぶ力を持つ素養を涵養する為に必要なものであることです。
羅針塾では、漢字を中心に語彙力が上がってくると、塾生には輪読の機会を設けます。たとえ小学生であっても、代わる代わる音読しているうちに、漢字熟語を読む力も増し、集中力も増してきます。
さて、インターネットで様々な記事を拝読しているうちに、参考になるブログを見つけました。
「日本漢文の世界」(https://kambun.jp/index.html)というサイトです。この中から興味深い記事をご紹介します。
(22)漢文訓読を現代に活かすために(「素読」から文法理解へ)
(前略)
現代において、この漢文訓読を活かしてゆくためには、何が必要でしょうか?
まず、江戸時代から明治の初期までと現代とでは、漢文の素養がまったく異なることを考えなければなりません。当時の教育では、子供にたくさんの中国古典を「素読(そどく)」させていました。「素読」とは、細かな意味は教えず、ただ声をだして漢文を訓読させる教育法です。大量の漢文を素読しているうちに、自然と漢文の意味が分かるようになるのです。もちろん、その域に到達するためには、非常に時間と労力をかける必要がありました。そして、このような悠長な教育法の実践は、明治以後には難しくなったため、「素読」は、今では全く廃れてしまいました。
(中略)
具体的にどの程度の素読が課されていたのか、宇野哲人・乙竹岩造・外著『藩学史談』(文松堂書店)の記事から見てみましょう。
津藩・有造館(三重県) 対象年齢 9歳~15歳
論語 孟子 詩経 書経 易経 礼記 春秋左氏伝 十八史略 史記 前後漢書 綱鑑易知録 資治通鑑 (同書12ページ参照)
仙台藩・養賢堂(宮城県) 対象年齢 8歳~三度落第したら退学
孝経 小学本註 四書集註 近思録 春秋胡氏伝 公羊伝 穀梁伝 周礼 太載記 (生徒の望みにより、史記 漢書 等も教授)(同書369ページ参照)
長州藩・明倫館(山口県) 対象年齢 8歳~14歳
孝経 大学 論語 孟子 中庸 詩経 書経 易経 春秋三伝 礼記 小学(同書181ページ、191ページ)
さて、この明倫館の課業は厳しく、「小学生素読」の試験では、五経十一冊と小学四冊を「誤読遺忘」なきように覚えなければなりませんでした。これは容易なことではなく、合格者が非常に少なかったので、試験を分割して行うようにするなどの緩和策が講じられたほどであったといいます。(同書195ページ)
以上は各地の藩学の状況ですが、私塾でもほとんど変わらないカリキュラムで教育が行われていたようです。たとえば、福沢諭吉は少年時代に私塾で学んだ体験を自伝に書いていますが、次のような驚くべき勉強量です。(『福翁自伝』、岩波文庫旧版、23ページ)
白石(しらいし)の塾(じゆく)に居(い)て漢書(かんしよ)は如何(いか)なるものを読(よん)だかと申(もう)すと、経書(けいしよ)を専(もつぱ)らにして論語(ろんご)孟子(もうし)は勿論(もちろん)、すべて経義(けいぎ)の研究(けんきゆう)を勉(つと)め、殊(こと)に先生(せんせい)が好(す)きと見(み)えて詩経(しきよう)に書経(しよきよう)と云(い)うものは本当(ほんとう)に講義(こうぎ)をして貰(もらつ)て善(よ)く読(よ)みました。ソレカラ蒙求(もうぎゆう)、世説(せせつ)、左伝(さでん)、戦国策(せんごくさく)、老子(ろうし)、荘子(そうじ)と云(い)うようなものも能(よ)く講義(こうぎ)を聞(き)き、其先(そのさき)は私(わたくし)独(ひと)りの勉強(べんきよう)、歴史(れきし)は史記(しき)を始(はじ)め前後(ぜんご)漢書(かんじよ)、晋書(しんしよ)、五代史(ごだいし)、元明史略(げんみんしりやく)と云(い)うようなものも読(よ)み、殊(こと)に私(わたくし)は左伝(さでん)が得意(とくい)で、大概(たいがい)の書生(しよせい)は左伝(さでん)十五巻(じゆうごかん)の内(うち)三四巻(さんしかん)で仕舞(しま)うのを、私(わたくし)は全部(ぜんぶ)通読(つうどく)、凡(およそ)十一度(じゅうひとたび)読返(よみかえ)して、面白(おもしろい)処(ところ)は暗記(あんき)して居(い)た。
江戸時代の教育は、もちろん「素読」だけだったわけではなく、「会読」や「講義」もあるわけですが、これだけ漢文の勉強をするのは、現代においては困難です。
それでは、現代において、速成的に漢文の読解力をつけるには、どうすればよいのでしょうか? それには、英語の学習とおなじように、文法の理解が必要です。漢文法を習うことが、漢文読解力の向上のために、非常に有効なのです。
英語でも、文法にもとづいて内容を理解できなければ、「直訳」すらできません。漢文も同じで、文法の理解なしでは訓読(=直訳)を誤ることにもなりかねません。ですから、訓読法を堅持する立場からも、文法の学習を忽(ゆるが)せにすることはできないのです。
・・・漢文を学ぶには漢文法を学び、英文を学ぶには英文法を学ぶべきである、という意見に全くの賛意を表します。
英語教育で所謂「読む」「書く」「聞く」「話す」の4技能を身に付けなければならないと喧伝(けんでん:盛んに言いふらすこと、世間で喧しく言い立てること)されています。
しかし、それには先ず国語力をつけなければならない。国語力をつけるには、国文法を身に付けなければならない。その上で、英語を学ぶ王道である英文法を身に付けるべきです。
詰まる所、国語力をつけるには、漢文教育プラス漢文法、国語教育プラス国文法、英語力をつけるには英語教育プラス英文法、となります。