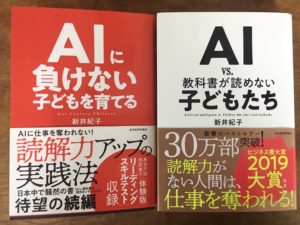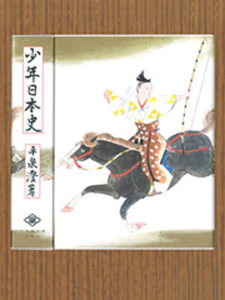様々な年代の子供さん達と接していると、その子の成長の為に家庭的な教育的背景が大きな力を持つことに氣づかされます。子供さんには、父母がありますが、そのまた父母、つまり父方・母方の祖父母があります。当然ですが、そのまた先祖となると、所謂(いわゆる)家系的に、子弟教育に対する熱意の濃淡が子供達にも投影されている様に思います。
子供の教育には、長い年月に亘る精神的・経済的な支援が必要です。歴史を振り返ると、日本人は他の民族と比較しても、子供を大事にするが故に、教育には熱心な民族といえます。日本が島国という恵まれた環境であり、地続きの国々と比べると、侵略される可能性は相対的に低いわけですから、長い年月に渡って、家系をつなぐことが出来ています。それ故に、言語も漢字は取り入れましたが、大和言葉を連綿とつないでいくことが出来ました。
有名な「最後の授業」(アルフォンス・ドーデの短編小説「月曜物語」の一編)には、国語を維持することの意義を示しています。
「最後の授業」のあらすじ(ウキペディアから引用https://ja.wikipedia.org/wiki/最後の授業)
ある日、フランス領アルザス地方に住む学校嫌いのフランツ少年は、その日も村の小さな学校に遅刻する。彼はてっきり担任のアメル先生に叱られると思っていたが、意外なことに、先生は怒らず着席を穏やかに促した。気がつくと、今日は教室の後ろに元村長はじめ村の老人たちが正装して集まっている。教室の皆に向かい、先生は話しはじめる。
「私がここで、フランス語の授業をするのは、これが最後です。普仏戦争でフランスが負けたため、アルザスはプロイセン領になり、ドイツ語しか教えてはいけないことになりました。これが、私のフランス語の、最後の授業です」。これを聞いたフランツ少年は激しい衝撃を受け、今日はいっそ学校をさぼろうかと考えていた自分を深く恥じる。
先生は「フランス語は世界でいちばん美しく、一番明晰な言葉です。そして、ある民族が奴隸となっても、その国語を保っている限り、牢獄の鍵を握っているようなものなのです」と語り、生徒も大人たちも、最後の授業に耳を傾ける。やがて終業を告げる教会の鐘の音が鳴った。それを聞いた先生は蒼白になり、黒板に「フランス万歳!」と大きく書いて「最後の授業」を終えた。
・・・筆者は、小学校の教科書で「最後の授業」を学び、子供心に戦争で負けると教科書や言葉も変わるのだ、と強烈な印象を持ったことを覚えています。
さて、子供の教育です。
私達のご先祖は、幾多の困難を乗り越えながら、私達に生命を繋ぎ、教育も繋いできています。親御さん方が、今ある自分の境遇を考え、親や祖父母、そのまた先のご先祖様方に想いを馳せると、自らの子供を如何により良く育てていかなければならないか、が見えてきます。
塾生に、分かる限り家系図を調べてみたら、自分のこれからの志を見つけることができると思います、と伝えたことがあります。
そうすると、何かを感じた塾生は早速取り組みました。夏休みの宿題の一環として、家系図を作成したり、親御さんに質問したり・・・すると、将来の目標として、四代目を継ぎたいという塾生もあらわれました。
やはり、自分のルーツ(root:根、〔~s〕(人などの)根っこ、出身、出自、祖先)の一端が分かると、自分も次に繋げていく存在であることに氣付かされます。
結局、これが子供さんの強く学びたいという動機付け(motivation:自発性、積極性、動機を与えること)になります。つまり、親御さん方自身が、御両親や御祖父母のことを理解し、尊敬することが、子供さんの学ぶ意欲を増す原動力になっていくのです。