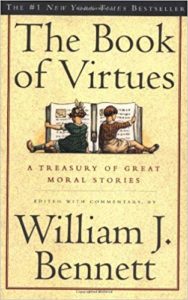明けましておめでとうございます。
平成三十一年が始まりました。本年は約二百年ぶりの天皇陛下のご譲位とそれに伴う改元が有る歴史的な年です。
そこで、日本の歴史を振り返ってみると、我が国は神話の時代から現在までの世界に比類のない継続性を持っていることがわかります。
今話題の百田尚樹著「日本国紀」(幻冬舎)の第1章「古代〜大和政権誕生」の冒頭を引用します。
日本の古代史を語る上での大きな障壁は、六世紀以前のことがよくわかっていないことだ。考古学的な資料を除けば、『魏志』をはじめとする中国の史書と、『古事記』と『日本書紀』が文献資料のほとんどすべてである。しかし、中国の史書における日本の記述には伝聞や憶測が多くあり、『古事記』と『日本書紀』にも神話が多数含まれているため、どこまでが事実かはっきりしない。
ただ、私がむしろ素晴らしいと感じている点はまさにそこで、日本の歴史は神話と結びついているからこそ、格別にユニークなものとなっているのである。古代ギリシャも神話と結びついている国といえるが、ギリシャは紀元前には滅んでしまった。ところが、我が国、日本は神話の中の天孫の子孫が万世一系で二十一世紀の現代まで続いているとされている。こんな国は世界のどこにもない。
しかも『古事記』も『日本書紀』もただの作り話ではない。そこここに考古学的な裏付けのある話が鏤(ちりば)められている。
そもそも神話というものは、実際に起こった出来事が暗喩を用いて象徴的な物語として描かれていたり、別の何かに置き換えられて書かれていたりすることがよくある。一見荒唐無稽に思える話の中に、真実が隠されているのが神話なのだ。
(後略)
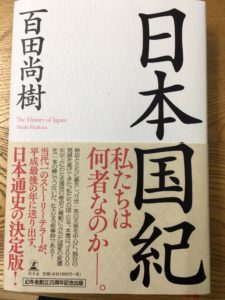
「日本国紀」百田尚樹著(幻冬舎)
・・・塾生と学びの合間にする会話の中で、御両親や御祖父母、そのまた先の御先祖のことを話す機会があります。当然会ったことのない現在の自分に繋がる御先祖に想いを致すことが、我が国の歴史や文化を学ぶ切っ掛けとなります。