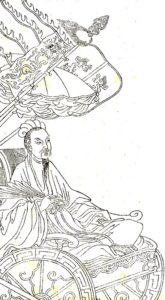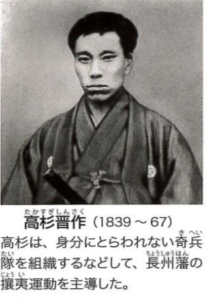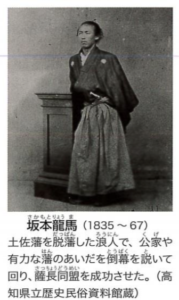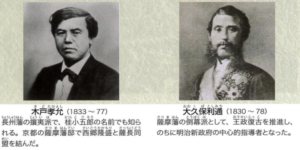長崎市五島町にある学習塾・幼児教室 羅針塾 https://rashinjyuku.com/wp では、熱中症対策として夏期講習の合間にリフレッシュ・タイムがあります。気分転換と暑い夏を乗り切る秘策です。その後、サッパリして自己啓発の為の「学び」再開です。
さて、戦後73年目の夏、八月六日・九日の原爆忌に合わせたかのように、以下の記事が掲載されました。産経新聞からの引用です。2018.8.9(https://www.sankei.com/life/news/180809/lif1808090028-n1.html)

チャーチルとルーズベルトがカナダ・ケベック州で原爆を共同開発すると決めた秘密協定「ケベック協定」
原爆投下でチャーチル英首相が7月1日に最終同意署名 1945年の秘密文書
【ロンドン=岡部伸】第二次大戦中の1945年7月、英国のチャーチル首相(当時)が米国による日本への原爆使用に最終同意して署名していたことが、英国立公文書館所蔵の秘密文書で判明した。約1カ月後の広島と長崎への原爆投下に至る意思決定に、チャーチルが深く関わっていたことを裏付ける資料として注目されそうだ。
同館所蔵ファイル(CAB126/146)によると、原爆開発の「マンハッタン計画」責任者、グローブス米陸軍少将が45年6月初め、英国側代表のウィルソン陸軍元帥を通じて英政府に日本に対する原爆使用を許可するよう求めた。
打診は、米国が核兵器開発に成功しても英国が同意しなければ使用できないなどと定めた43年8月の「ケベック協定」に基づく。
英政府内で検討を重ねた結果、チャーチルは容認を決断し、45年7月1日、「オペレーショナル ユース オブ チューブ・アロイズ」(米国が日本に原爆を使用する作戦)に署名した。英首相官邸はこの最終判断を同2日付で公式覚書とした。
同4日、米ワシントンで開かれた原爆開発の相互協力を協議する「合同政策委員会」の席上、ウィルソンが英政府として公式に「日本への原爆使用に同意する」と表明したことが分かっている。同ファイルによると、ウィルソンは米側に、チャーチルがトルーマン米大統領と近く直接協議を望んでいるとも伝えた。
また別のファイル(PREM3/139/9)によると、7月24日のポツダム会談でチャーチルは、44年9月にトルーマンの前任のフランクリン・ルーズベルトと日本への原爆使用を密約した「ハイドパーク協定」を持ち出し、「警告なしで使用すべきだ」とトルーマンに迫った。
トルーマンは翌25日、原爆投下指令を承認、投下命令が出された。その結果8月6日、人類史上初のウラン原爆が広島に、9日にはプルトニウム原爆が長崎にそれぞれ投下された。
チャーチルが最終容認した背景には、英国が米国に先行し原爆開発に積極的に関与してきたことがある。
30年代から亡命ユダヤ人科学者によって核分裂や核融合反応で放出されるエネルギーを利用した新兵器研究が進められ、40年にウラン235単独で爆弾が製造可能という理論をまとめた。41年10月、英独自の原爆開発計画「チューブ・アロイズ」が始動。米国に開発推進を訴え、42年8月、「マンハッタン計画」が始まった経緯がある。
さらにファイル(PREM3/139/9)によると、チャーチルが44年9月、米国内のルーズベルトの別荘を訪れた際に結んだハイドパーク協定で、2人は「原爆が完成すれば、熟慮後、おそらく日本に使用される」などと合意した。原爆完成後はドイツではなく日本へ投下することが米英で密約され、翌10月、米国は原爆投下の最終準備に入った。
◇
■ケベック協定 1943年8月、ルーズベルト、チャーチルの米英首脳はカナダ・ケベック州で原爆の共同開発を密約。(1)兵器(原爆)を互いに対し攻撃するため使用しない(2)第三国に使用する場合、互いの同意が必要(3)両国の同意がない限り、英原爆開発計画「チューブ・アロイズ」に関する情報を流さない-などと結んだ。(2)は英側の事実上の拒否権となった。

チャーチル(ゲッティ=共同)

米国による対日原爆投下の作戦文書に記された英国のチャーチル首相の署名(岡部伸撮影)
・・・現在の日本人の多くが全く知らないだろうという記事です。
チャーチルは、偶然かのように歴史上の偉大な人物として最新の映画が上映されています。→
本年度アカデミー賞受賞(主演男優賞/メイクアップ&ヘアスタイリング賞)「ウインストン・チャーチル(ヒトラーから世界を救った男)」 「嫌われ者」から「伝説のリーダー」となったチャーチルの、真実の物語。http://www.churchill-movie.jp
・・・と、同映画の公式サイトはキャッチ・コピーを高らかに掲げています。原題は「DARKEST HOUR」、即ち「真っ暗闇の時間」。確かに、英国を守るために様々な苦渋の決断をしてきている偉大な宰相です。英国にとっては。
しかし、立場が変われば、国際政治の苛酷な現実が上記の昭和二十年(1945)七月一日の英国首相チャーチルの「原爆投下へ最終同意署名」です。
その当時の日本はほとんど継戦能力がなく、終戦へ向けての外交交渉は、まるで米国を中心とする連合国に弄ばれているかの如く、手の内を見透かされた中で必死に行なっていました。まるで、日本以外の連合国のプレイヤーが日本の手札を刻々と見透かしレートを吊り上げている中で、日本はポーカーをしているようなものでした。
八月六日の広島への原爆投下、それに続く九日の長崎への原爆投下、日ソ不可侵条約を破ってのソビエト連邦の対日参戦。
その日本を取り巻く情勢の厳しい悪化の中で、昭和天皇は終戦への大英断を下され、日本民族が生き残る道を選ばれたのでした。