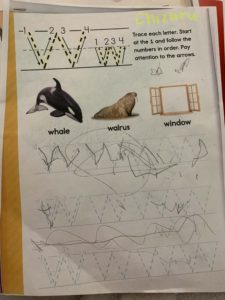長崎市五島町の就学前教育(プレスクール)・学習塾の羅針塾では、小学校英語が科目化される以上、足が地に着いた英語を学ぶべきだと考えています。
さて、
都麦出版のメルマガ(つむぎNEWS)に以下の記事が掲載されていましたので、引用してご紹介します。
京都府下で塾をされている先生から,中1英語の中間テストの問題のコピーを頂きました。それを見て,「やはり想像していた通りだ!」と思いました。それはそのテスト問題が,従来実施されてきた中間テストのものと比べ,格段に難しくなっていたからです。例えば,そこにはこんな問題も載っていました。「新しく来られたAETのJamie先生に,自分のことを知ってもらうための自己紹介を,英語で5文以上書きなさい。」
この問題で得点できるようになるには,テストの現場で「次のような英作文を書ける」という力が求められます。
My name is Minoru Torii.
I live in Kyoto.
I like tennis very much.
I have a sister.
Her name is Tomoka.いかがでしょうか。
小学校では耳から聴き取る英語の学習がほとんどで,英文法の学習は皆無といっても言い過ぎではありません。そのような環境下で英語教育を受けてきた子どもたちが,中学に入って2カ月もしないうちに,このような英作文を書けるようになるのでしょうか。
子どもの気持ちになってみれば,「何これ!いきなりこんな問題を出されてもできるわけないよ!」ということにならないでしょうか。
・・・懸念していた通りです。
一握りの英語のできる生徒と、英語嫌いになる多数の生徒に二極分化するであろうということです。
つまり、小学校の英語の授業では、「楽しく英語に親しもう」というconcept (/kάnsept|
kˈɔn‐/ 構想、発想、考え)ですから、英単語の暗記、英文法、英作文など全くと言って良いほど触れられていません。
それなのに、中学校に入学した途端、英単語の暗記、英文法、英作文は必須です。これを前提に、定期試験や実力テストが始まります。
結局、小学校の中途半端に「英語は楽しい」授業ですという世界から、一転して百点満点で何点取れますかという中学校の厳しい現実の世界に放り込まれて仕舞います。
その様な小学校英語と中学校英語のギャップをどの様に乗り越えていくか、が問題です。
その為の対策は、小学校の英語と連動して英文法や英単語の暗記、英作文を学ぶことに尽きます。